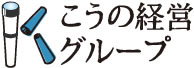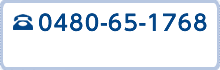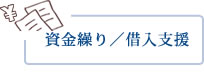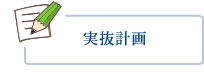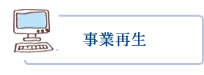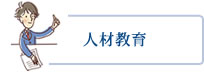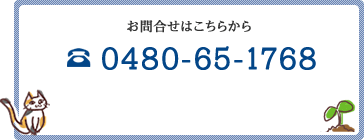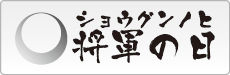経営支援
| 長年にわたるお付き合いのなか、幾度となく直面するクライアントの経営危機に対して「何とかできないか!?」との思いで、会計事務所の通常業務から脱線する形で担当部署を設け、専任者を2人3人と増やしてきました。現在のMAS営業部です。MASとはマネジメント・アドバイザリー・サービス、文字通り「経営支援」を意図しています。 |  |
既存のクライアントだけでなく、中にはHPをみて困り果てて駆け込んでくる方もいます。またそれ以上に、ご紹介をいただく形で質的・量的にサービスの領域も拡大してきました。経営者にとことん寄り添い、土日だろうと深夜早朝だろうと、納得いくまで何度でも話し合って結論を出したい。どんなお客様であっても、こうの経営を頼りにして下さる限り、その利益の最大化を目指して懸命に取り組みます。
資金繰り/借入支援
・銀行からの借入返済を少なくしたい
・もう今月の返済すら厳しく迅速に返済計画を見直したい
・リスケジュールを試みたが、資金繰り表など銀行から提出を求められる資料作成がうまくいかない
・リスケしたら今後銀行から融資を受けられないのではと、デメリットの部分で悩んでいる
あなたはこのサービスで下記の結果を得ることができます。
・毎月の返済をストップまたは減額できます
・銀行の審査に通る資料が作成できます
・リスケジュールに関する不安を払しょくできます
当サービスの強みと特長をご紹介いたします。
1.元銀行員としての交渉力でリスケジュール
銀行への要請内容、タイミング、決算書、資金繰り状況など、様々なポイントを抑えプランを練り、事前に十分な説明を行い、ご安心いただいた状態で、銀行へ一緒に向かいましょう。
2.リスケジュールを完了させる方法だけでなく、その先の事業の展望を描きます
例えば返済をストップさせたから解決というわけではありませんよね。
経営は続いていき、リスケジュールにより借入が消える訳でもありません。
半年後・1年後・3年後・・・財務分析を行い、未来が描ける状態まで、徹底的にサポートいたします。社長は営業活動など前向きな方向へ力を注いでいきましょう。
|
こんな場合はセカンドオピニオンの利用を ・顧問税理士は申告書作成だけで、経営相談は応じてくれない ・多くのアドバイスの中から、より最適な解決策を自分で選択したい ・付き合っている専門家には経営改善や資金繰りは専門外だ ・今付き合っている専門家は偉そうな態度で相談がしづらい ・そもそも相談できる専門家がいない |
 |
このようなお悩みを持つ経営者様には、セカンドオピニオンの存在は非常に役に立ちます。税務面については、当社の提携税理士が対応します。なお、今お付き合いされている税理士や経営コンサルタントとの顧問契約を解除して頂く必要はありません。
銀行融資取引・資金調達に関するコンサルティング
私が今まで多くの経営者の方々とお会いして感じるのは、売上高(または利益)や節税はとても気にするのですが、資金繰り管理や銀行との上手な融資取引に関しては疎かになっている場合が多いということです。
儲かっていてもそうでなくても、多くの中小企業は常に資金繰りの悩みが付きまといます。
そこで当社では、家族経営のような小規模企業から中規模企業までを対象にし、銀行融資による資金調達や資金繰りに関するコンサルティングを実施しております。
当社は経営者様と同じ立場になって「経営(改善)計画書」「資金繰り表」や「試算表」といった融資申し込みに必要な書類作成支援、銀行等金融機関との融資取引・銀行交渉についてのアドバイス・支援を行い、資金繰りや銀行との上手な付き合い方のサポートを行っています。
実抜計画(経営再建、経営改善計画)
実抜計画とは、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」のことです。銀行は、その計画を基に「支援を続けるか、打ち切るか」といった判断を行います。要するに、「うまくいく見通しを、冷静に、分かるようにしてね」ということです。こうの経営では、実抜計画を「どうやって作るのか」「金融機関に対する見せ方」といったことについて、作成のお手伝いをしています。
経営計画は、航海を続けるために欠かせない<会社の羅針盤>です。1年後、5年後、10年後・・・どんな会社になっていたいのか、社長の想いをコトバにして他人に伝える<未来予想図>でもあります。ぼんやりした計画よりも、出来るだけ細かく落とし込まれた計画のほうが、より第3者に説得力があるに決まっています。
さらに、経営計画は銀行からお金を借りるために存在するのではなく、自社の業績を改善させるための<予算案>です。ライバル企業と比べて、粗利率や労働分配率、経常利益率は適正かどうか。劣っているのであれば、どこの数値を改善すれば見劣りしない内容になるのか。この<予算案>があって初めて議論のたたき台になります。
加えて、経営計画は幹部が価値観を共有するための<シンボルマーク>にもなります。社長が彼らとコミュニケーションを取る際に、必ず役立つはずです。
|
我々は、専用システムを活用し、年間に30件以上もの経営計画の作成をお手伝いしています。また、自分たちでも計画を作り、毎年スタッフと共有しています。「計画はあるんだけど、ホコリかぶっちゃって・・」ということにならないように、作った経営計画に命を吹き込むために、第3者のコンサルタントの力を利用してはいかがでしょうか。
|
 |
事業承継/M&A
事業承継は、経営者の最後の大仕事といえます。経営者にとって我が子同然の会社を、「誰に」「いつ」「どのように」
引き継ぐか、我々も最近では多くの相談を受けるようになりました。
かつては、中小企業は「家業」として息子が継ぐのが当然でした。いまではオーナー企業のうち68.8%が後継者不在といわれています。また、長引く不況で事業承継を先送りしてきた企業も多数く、経営者の平均年齢は右肩上がり(2012年は平均58.7歳)です。
後継者が決まっている場合でも、事業承継にはとても時間がかかります。しっかりとプランニングをして、後継者にスムーズな引き継ぎを行うことが必要です。また、事業承継と相続対策は表裏一体の関係にあり、自社株式の相続・遺贈等の法律面と、相続・贈与・財産評価といった税務面をそれぞれ両面で考慮しなければいけません。
オーナー企業では、誰が後継者になる?
| 後継者 | オーナー企業 | 全企業平均 |
| 配偶者 | 17.2% | 14.6% |
| 子ども | 56.0% | 42.6% |
| その他親族 | 18.3% | 19.2% |
| 他人 | 8.5% | 23.6% |
| 合計 | 100.0% | 100.0% |
M&A
ここ数年で随分と身近になったのがM&Aです。従来の同族承継ではない新しい選択肢として活用されることが増えてきました。売上1億円未満の中小零細企業も例外ではありません。友好的なM&Aで経営資源の豊富な企業グループに加わることにより、販路の拡大・円滑な資金調達など、自社の弱点を補うことができます。社員の希望にもなるでしょう。
その他、他人の役員・従業員への承継を志向するケースも増えています。いずれのケースでも、克服すべき課題は山ほどあります。じっくりと時間をかけて譲り渡す側、譲り受ける側と話し合い、オーナー経営者は満足のいく退職金を手にしてハッピーリタイヤを、承継した人は完全に自分の会社として出発ができるように、こうの経営があらゆるリスクを点検して“工程表”を作成します。
事業再生
「決算書を粉飾して融資を受けているが、借金返済の終わりが見えない・・」
「従業員の給料が払えない/退職金の積み立てにも手を出してしまった・・」
「個人でお金を工面して回してきたが、もうどうにもならない・・」
「家族に隠れて〇〇金融から借りてしまっている・・」
事業再生とは、借入等の負債がその財産を超過して会社のお金が回らなくなるという「倒産」状態から、文字通り「会社を生きかえらせる」手続のことです。具体的には、過去の負債(買掛金・借入金など)を圧縮あるいは0にすれば資金繰りが回り、支払が正常化していくのではないかとういうのを検討し、スキームを構築して、金融機関その他の利害関係者と時間をかけて交渉していくという流れです。特に、ここ最近では税務的にも新たな法整備がなされ、再生を後押しする仕組みができつつあります。
経営者には、冒頭のようなことにならないように、会社の資金が枯渇する前の「早めの対応・決断」が望まれます。歴史のある、地域に貢献してきた会社を守りつつ、取引先・従業員・金融機関に対してなるべく迷惑をかけないようにすることが事業再生を行う上で大変重要なことです。
こうの経営では、案件ごとに弁護士(リーガルチェックや債権者集会)や、事業の将来見通しを判断するために中小企業診断士などとチームを組み、社長の傍らで、会社の内部からその実現に向けて動いております。
人材教育
収益の悪化している会社の社員は、「利益を残し、お金を増やす」という会社の根源的な目的を理解していません。社員は就業時間内にこなすべき仕事を理解しているだけで、会社全体のなかで自分がどの役割を果たしているのかを知りません。一方で、過剰な目標(ノルマ)が課せられ「達成できなければ減給」と言われます。
このような状況下では、社員は目標が達成できないどころか、会社に対して不満を募らせていきます。これを、私たちは(1)経営幹部の無知、(2)現場管理者の無知、(3)一般社員の無知、として速やかに改善すべき事態と捉えています。こうなってしまったら、もはや双方お互いに嫌悪感を抱くだけで、社内での改善は不可能です。私たちが外部のコンサルタントとして現場に張り付き、当事者全員から聞き取り調査をして、この無知が生む嫌悪感を取り除いていきます。
・利益概念を理解するための「計数教育」
・目指すべきリーダー像を定義する「リーダー研修」
・自分自身の特性を知るための「適性検査」
・部下を目標管理するための「ビジネスコーチング研修」
このような研修を通して管理者や社員の仕事に対する意識改善を行い、「言われたことをこなすだけの社員」から「全社的な視点から、目的をもって付加価値を創造できる社員」に生まれ変わります。こうの経営では、1年間(毎月1回×12ヶ月)の単位で、幹部に対する研修を請け負っています。
これからは中小企業でも、自社の人材を“人財”として活かすことを積極的に考えるべきです。過去には後継者教育の実績もあります。また、結果を残すための「人事評価制度」の作り直しもお手伝いさせていただいております。「教育」に関するお悩みがありましたら、ご相談ください。
対応地域 加須市・久喜市・羽生市・行田市・さいたま市・古河市・館林市・その他
さいたま・戸田・蕨・川口・朝霞・草加・和光・志木・清瀬・所沢・川越・桶川・富士見・三芳・吉見・ふじみ野・北本・鴻巣・白岡・蓮田・岩槻・春日部・越谷・杉戸・宮代・幸手・野田・松戸・八千代・小山・宇都宮・壬生・結城・佐野・つくば・秩父・小鹿野町・深谷・前橋・伊勢崎・藤岡・本庄・富岡・安中